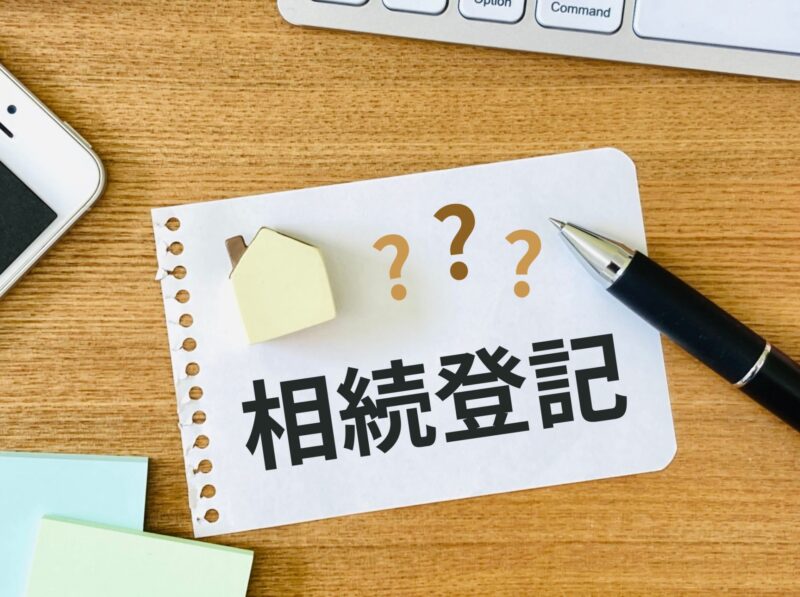相続とは
身内の方が亡くなられたとき、亡くなられた方(被相続人)の有していた不動産、預貯金、株式等の財産や借り入れ金等の債務は、一定の親族の方に承継されます。
このような財産等の承継を相続と呼びます。
そして、不動産を所有している方に相続が発生した場合、その不動産の所有権を取得した方への所有権移転登記をする必要があります。
よく名義変更と表現されたりしますが、実は変更登記ではなく所有権の移転登記です。このような相続の場面での所有権移転登記が相続登記と呼ばれています。
相続登記はしなければいけない?
2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化されました。
相続が開始し、不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記を申請しなければならず、これをしない場合10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
相続登記をすることは、法律上の義務であり、しなければならないことといえます。
相続登記をしないとどうなるの?
そのうちやればいいか、と相続登記を後回しにしておくとどうなるのでしょうか?
相続登記を後回しにしておくと、相続手続が困難となったり、より手間や費用がかかってしまうといったことになりかねません。
そういったことが起こりがちないくつかのケースをご紹介します。
ケース① さらに相続が発生する
相続登記をせずにいる間に、相続人のうちのどなたかが亡くなるようなケースを数次相続といいます。
この数次相続が発生すると手続に関与すべき相続人がどんどん増えていき、相続の手続が複雑化してしまいます。
戸籍等の書類収集が大変になるうえに、普段付き合いのあまりない親族が相続人となることも多く、話し合いがまとまらず遺産分割協議がスムーズにいかなくなる可能性も高くなりがちです。
数次相続が何度も生じているようなケースでは、相続人の数が数十人になることもあり、ケース②で紹介する判断能力が低下してしまっている相続人もいたりと、手続が非常に困難な状況も生じてしまうこともあります。
ケース② 相続人の判断能力の低下
相続の手続を後回しにしている間に、相続人の誰かが認知症等により判断能力が低下してしまうことがあります。
判断能力の低下の程度によっては、有効な遺産分割協議をすることができなくなることもありえます。
そうすると、法定相続分での共有とするか、成年後見制度を利用し後見人等に遺産分割協議をしてもらわなければなりません。
ただ、法定相続分での共有とすると、共有者の意思能力の問題から売却や担保提供等が困難となってしまいます。
一方で、成年後見制度を利用すると、遺産分割協議が終わったあとも制度の利用をやめることはできません。選任された後見人が専門職であった場合や後見監督人が選任された場合、後見人等の報酬を払い続けなければなりません。また、後見人は、被後見人の不利益となるような遺産分割協議はできないため、家族の間での実情を考慮した遺産分割にはならない可能性もあります。
夫や妻が亡くなった場合、残された配偶者も年齢が近いことが多く、判断能力の低下が生じてしまうケースは多くあります。こういったケースでは残された配偶者の生活設計にも影響を及ぼしかねません。
ケース③ 相続人の中に借金のある人がいる
被相続人が亡くなると、遺産分割協議がなされるまでの間、相続財産は相続人全員で共有されている状態となります。
ここで、相続人の中に借金のある人がいる場合、その相続人の持っている共有持分を債権者が差し押さえてしまうことがありえます。そうなってしまうと、差し押さえられた持分については、遺産分割協議をしても債権者に対抗することができず、相続の手続に支障が出てしまうこととなってしまいます。
相続登記はお早めに
相続登記を後回しにしておくと、これらのケースのような事態が生じてしまうことがあります。
相続登記はできるときに、お早めにしておくことが重要です!